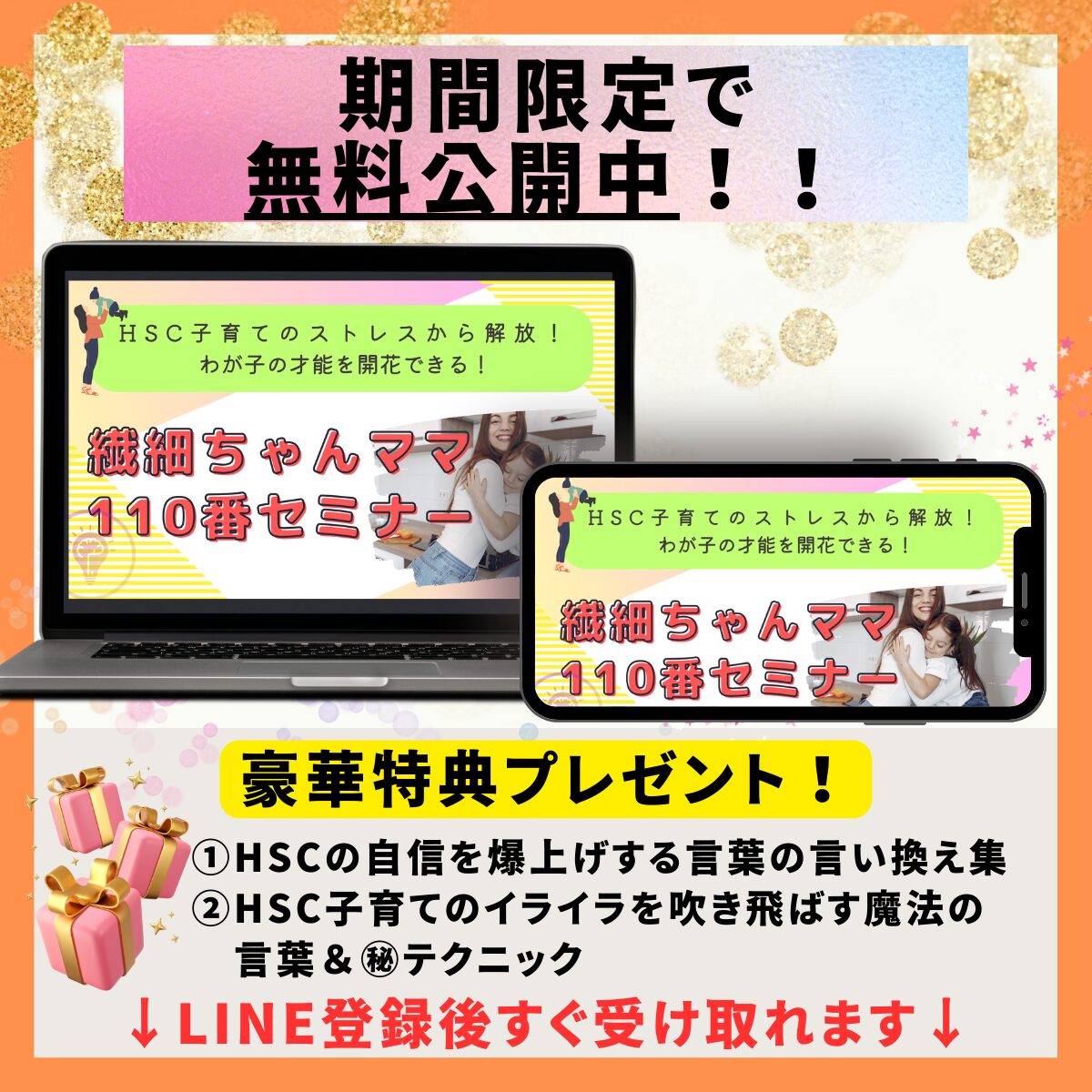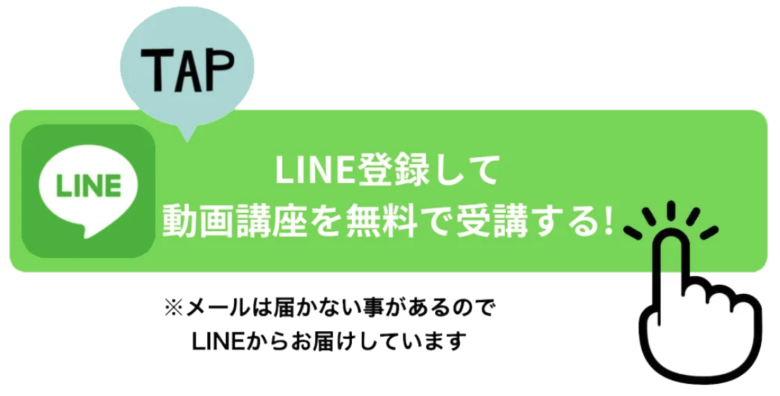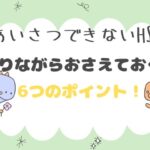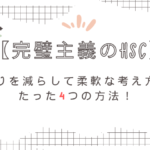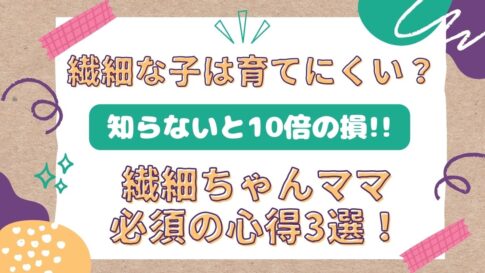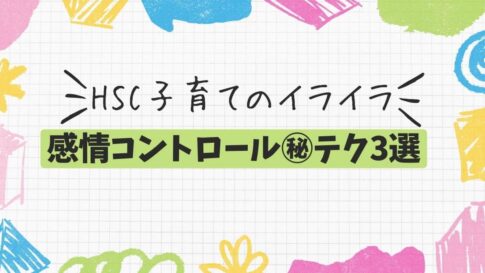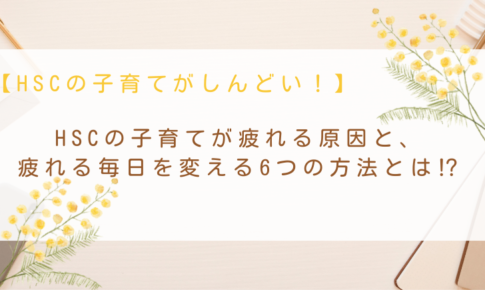HSCのお子さんの癇癪で悩まれていませんか?
HSC(Highly Sensitive Child)のお子さんは、過剰に刺激を受けやすい気質を生まれつき持っています。
その敏感な性質から、周りが


そんな親御さんに、いざ癇癪をおこしたときにとる対応を4つお伝えします。
- 落ち着いて冷静になる
- ひどい癇癪の時は少し離れる
- 癇癪に対して辞めさせたりりつけない
- お子さんの気持ちを言語化する
また、HSCのお子さんが癇癪をおこさないようにしていくための、親御さんができる4つの方法があります。
- 環境を整える
- 言葉で伝えられることを教える
- お子さんの話を聞く
- 失敗しても大丈夫と伝える

HSCが癇癪をおこす3つの理由

HSCのお子さんが癇癪をおこす理由として、HSCの特性によるものがあります。
- 完璧主義で自分を追い込んでしまう
- 刺激に敏感ですぐに疲れてクタクタになってしまう
- 些細なことにも敏感に察知して不安を感じやすい
完璧主義で自分を追い込んでしまう
HSCのお子さんは、0か100で考えてしまう完璧主義が多いのです。

「ちょっとの失敗もゆるせない!」
刺激に敏感ですぐに疲れてクタクタになってしまう
HSCのお子さんにとって、園や学校はとても刺激の多いところであり、行くだけでもとても疲れてしまいます。
園や学校に限らず、外出するだけ、人と会うだけでもHSCのお子さんは疲れ果ててしまうのです。

疲れがたまっているところに、さらに刺激が加わってしまえば、心も体もいっぱいいっぱいになってしまい癇癪をおこしてしまうのです。
些細なことにも敏感に察知して不安を感じやすい
HSCのお子さんは、1を聞いて10で受け取ってしまったり、ちょっとした変化にも敏感に察知します。

自分が怒られたわけではないのに不安になってしまう、不平不満を感じやすい、こういった感情が癇癪をおこしやすくなってしまうのです。
HSCのお子さんが癇癪をおこしているときは、不安や辛いと言った何かしら心身が傷ついている状況です。
HSCは外ではいい子、家では暴れる理由
 実は、外ではいい子なのに家では癇癪で暴れてしまうというHSCのお子さんは多いのです。
実は、外ではいい子なのに家では癇癪で暴れてしまうというHSCのお子さんは多いのです。
園や学校で「とてもいい子」と聞いてびっくりしたという親御さんもいらっしゃるでしょう。

ではなぜ家では暴れてしまうのでしょうか。
それは
- 外では頑張っていい子になっているから
- 家は甘えられる唯一の安全基地だから
なのです。
それぞれ説明していきますね。
外では頑張っていい子になっているから
HSCのお子さんは周囲の空気感や相手の気持ちをよく読み取ることができます。

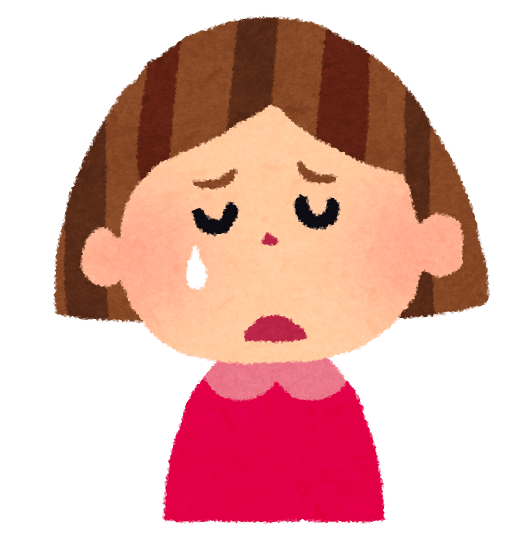
「この係をやりたいけど、さっきあの子やりたいって言ってたから譲ってあげた方がいいかな。」
「ケガしちゃってまだ痛いけど、先生が困るかもしれないから『大丈夫』と言っておこう。」
家庭ではお子さんの言いたい事や、やりたい事を口に出さなくても理解してもらえたり、「仕方ないなあ」と甘やかしてもらえたりしますが、園や学校ではそうはいかないことを分かっているのです。
家は甘えられる唯一の安全基地だから
お子さんにとって、家庭や親御さんは甘えられる安全基地です。
安心できるからこそ、甘えられることができ、自分の感情を伝えることができます。

HSCの癇癪への対応4選

では、いざお子さんが癇癪をおこしたときは、親としてどう対応したらよいのでしょうか。
それは
- 落ち着いて冷静になる
- ひどい癇癪の時は少し離れる
- 癇癪に対して辞めさせたり叱りつけない
- お子さんの気持ちを言語化する
それぞれ説明していきますね。
落ち着いて冷静になる
親御さん自身が落ち着いていなければ、お子さんを落ち着かせることは難しいものです。

しかし、お子さんといえども、言葉や暴力で攻撃されてしまえば、親であっても心穏やかにはいられません。

ひどい癇癪の時は少し離れる

近くにいてなだめようとしても、興奮状態で親御さんの声は届きにくい状態です。

HSCのお子さんは周りの刺激を敏感に感じてしまう特性があります。
できるだけ刺激を少なくしてあげるために、そばから少し離れ、声掛けも最小限にしてあげると良いでしょう。
しかし離れると、
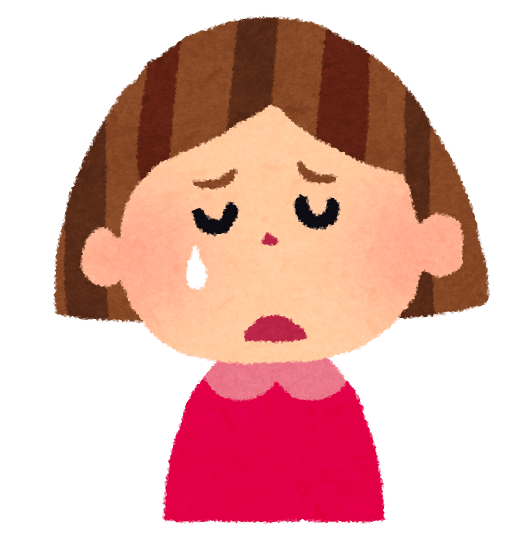
そんな時は離れることはできませんが、ただそこに「居る」だけにし、なだめたり言葉などの刺激は最小限にしましょう。

癇癪に対して辞めさせたり叱りつけない
HSCのお子さんが癇癪をおこしているときは、「不安」や「辛い」と言った何かしら心身が傷ついている状況です。
そんな時に、無理やり


癇癪時に、癇癪をやめさせようとしたり、りつけることはやめましょう。
お子さんの気持ちを言語化する
お子さんが少し落ち着いてきたら、お子さんの気持ちを言葉にしてあげましょう。

「思ったようにできなくて、悲しくなっちゃったんだね」

HSCが癇癪をおこさないための4つの方法

HSCのお子さんが癇癪をおこす理由や、癇癪がおきた時の対応をご説明しました。
そうはいっても、

できることなら、癇癪はおこさないでほしいものです。
お子さんが成長していくなかで、葛藤を自分で折り合いつけることが出来てくるため、癇癪は徐々に落ち着いていきます。

それは
- 環境を整える
- 言葉で伝えられることを教える
- お子さんの話を聞く
- 失敗しても大丈夫と伝える
これらの方法を親御さんがとることで、HSCのお子さんは絶対的な安心感を得ることができます。

環境を整える
HSCのお子さんは些細な刺激にも敏感に反応します。
お子さんにとって刺激の多い環境は不快であり、不満が募りやすくなります。
心にも余裕がなくなってしまうでしょう。

言葉で伝えられることを教える
まだ小さなお子さんは、自分の気持ちを表現する方法を、泣いたり、癇癪といった方法でしか伝えられないことがあります。


「お腹すいたのかな」
「押されて嫌な気持ちになったんだね」
お子さんの気持ちを汲み取って適切な言葉を伝えていきましょう。
たくさん話をすることで、お子さんは

お子さんの話を聞く
HSCのお子さんは、園や学校で色々と我慢したり、不安を感じています。
安心できる家に帰ってきたら、その不満をぶつけてくるかもしれません。

お子さんが園や学校、人のことを悪く言っていると、

「勘違いじゃないの」
「こうしたらいいんじゃない」
しかし、そこは我慢して、お子さんの話を最後まで聞いてあげましょう。
HSCのお子さんは、人の悪口を言ったり、相手に不快な思いをさせることは良くないと理解してます。

しっかり気持ちを吐き出させてあげましょう。

「○○くんがそう言ったんだね」
「それはつらかったね」
「他にもなにかあった?」
「嫌な気持ちになったね」
親御さんが話を聞いてくれることで、


失敗しても大丈夫と伝える
先述したように、HSCのお子さんは完璧主義が多く、何かを達成できなかった時に癇癪をおこすことがあります。
普段から

「何かあればママが助けてあげるから大丈夫」
「今はできなくても、大きくなったらできるようになるよ」
繰り返し伝えることで、お子さんにも印象付けられ、いざ失敗をしても

まとめ

いかがでしたでしょうか。
お子さんにとって癇癪は、気持ちがいっぱいいっぱいになってしまった時に出てきてしまう感情表現です。

お子さんのこの辛い状況を落ち着かせるためには
- 落ち着いて冷静になる
- ひどい癇癪の時は少し離れる
- 癇癪に対して辞めさせたり叱りつけない
- お子さんの気持ちを言語化する
また、普段から癇癪をおこさないようにするための方法として、
- 環境を整える
- 言葉で伝えられることを教える
- お子さんの話を聞く
- 失敗しても大丈夫と伝える
上記をお伝えしました。
親御さんも日々の仕事や家事で気持ちの余裕がなくて、お子さんに寄り添えない時もありますよね。